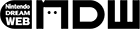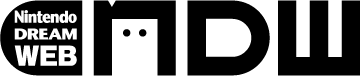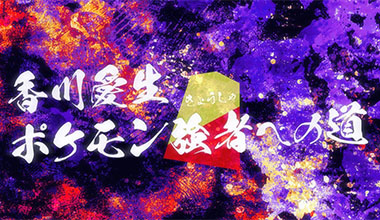やればやるほど ディスクシステム インタビュー(2004年9月6日号、9月21号より)

『パルテナの鏡』を開発中に、3日間の新婚休暇をもらって、2日目に呼び出されたんです。(大澤)
発売の3日前まで開発していた『パルテナの鏡』
── ワリオの生みの親である清武さんにとって、ディスクシステムとはどんな存在でしたか?
清武 書き換えできることがいちばんのアピールポイントで…。それで、「何でもできるよ」って言われてたんですけど、実際は…(苦笑)。
坂本 なんかヤバイ話になりそうやなあ(笑)。
清武 容量が増えるとか、いろいろいいことを言われたんですけど、もちろん限界がありましたし、僕にとっては仕事量が増えたような感じだったんです。
── (笑)
大澤 「仕事量が増えた」という話で思い出したんですけど、ディスクシステムってロムに比べて、工場での製造がとてもスピーディだったんです。だから、『パルテナの鏡』のときは発売の3日前まで仕事をしてたんですよ(笑)。
── そんなに直前までやってたんですか!?
大澤 「今日マスター版を出せへんかったら、発売が間に合わんよ」と言われたのが3日前だったんです。
── それでも間に合ったわけですね。
大澤 ディスクシステムの製造って、工場にずらーっとディスクライターが並んでいて、アルバイトの人たちが、カシャン、カシャンとディスクをさしては、抜いてという作業を人海戦術でやってたんですよ。
── フロッピーにデータをコピーするような感じで?
坂本 そうそう。やる気次第でできると(笑)。
一同 (笑)

── 1枚つくるのにどれくらいの時間がかかったんですか?
大澤 お店でみなさんがディスクライターでコピーするのと変わらないですから、ほんの数秒という感じですね。それで、最後の最後で「バグがこれでとれなかったらオシマイだあ〜」って。『パルテナ』の発売が確か12月19日で、その3日前にそんなことを言ってたんですよ(笑)。
坂本 日付まで、よう覚えてんなあ(笑)。
大澤 すごいでしょ(笑)。それで「クリスマスに間に合わへんのやったら、オマエどーする?」なんて言われたりもして。「クビにする」とまでは言われませんでしたけど(笑)。だから、スタッフみんなで悲壮な顔をしてつくってましたね。
坂本 たくさんのスタッフが、忘年会に徹夜明けのまま参加したような記憶があるなあ。
大澤 そうやったですね。とにかく悲惨な環境で(笑)。
坂本 当時は、やることが何でも激しかったんですよ。『パルテナの鏡』のときは、ちょうど大澤が結婚したばかりで。『メトロイド』なんかもそうだったんですが、最初は少数でつくりながら、開発の終盤になると一斉にみんなでまとめ上げるようなつくり方をしてるわけです。それで、みんなで『パルテナ』をやってるときに、大澤がいないので「あいつ、どうしたんやろう?」と聞いたら、「家に帰ったらしい」と言うわけですよ(笑)。
大澤 結婚する話は前から言うてたやないですか!(笑) それに、結婚する頃には開発は終わってるはずだったんです。でも、終わらなかったんです(笑)。だから、「結婚式は挙げるけど、新婚旅行は諦めました。でも、3日間だけお休みをください。家の片づけもしたいし」と言ってから休んだら…2日目に呼び出されて(笑)。
一同 (爆笑)
大澤 それも、当時の上司から電話がかかってきて、「大澤、悪いけど、悪いけど、ここまでがまんしたけど、どうにもならんから出てきてや」って言われて…。僕としても「…はい」と答えるしかなかったですね(笑)。
坂本 現場としても『メトロイド』が終わって、すぐ『パルテナの鏡』の開発に入っていたので、気が立ってたと思うんです。それで、「大澤、なにしてんのや。呼ぼか」という、そんなノリがあったと思いますね(笑)。それで「いま何してんの?」と聞いたらしくて、「メシを食ってます」って(笑)。夕食を食べてるときに呼び出されたんですよ(笑)。
大澤 それで嫁さんに「ごめん、仕事だから行くわ」って言って。
── 奥さんはすごく怒ったんじゃないですか?
大澤 いや、怒るというより、「そんなもんなんや」という感じでしたね。ゲームをつくる仕事はそういうもんなんだと思ってくれたようで。結婚当初から厳しい状況を経験すると、あとの規制がわりと緩くなるというか(笑)。
── うまいことやってますね(笑)。
坂本 それにしても、家で夕飯を食べている新婚さんを呼びつけるチームメイトってホンマにすごいなあ(笑)。
── 他人事のように(笑)。じゃあ、結局、新婚旅行もナシだったんですか?
大澤 行ってないです。当時はゲーム1本つくるのに、すごく情熱があったというか。こんな言い方をすると、いまは情熱がないように思われたらアカンのですけど(笑)。当時は「オレたちがやらなアカン!」という気持ちが前面に出ていた時代だったんですよね。

── 当時は少人数でゲームをつくっていたこともあって、そんな気持ちになったということですか?
大澤 そういうこともあったかもしれませんが、当時はディスクシステムにサードパーティがそれほど参入してきていなかったので、「自分たちがリードして引っぱっていかないと」という気持ちが強かったんです。
── なるほど。
大澤 僕にとって『パルテナ』はデビュー作なんです。それで、会社に入ってちょうど2年目くらいの新人に対して、1本任せてもらったということに対して、僕としても「やらなアカン」という気持ちにさせられましたね。自分を客観的に見たときに、入社して2年目の頃って、すごくやる気満々で、野心もありますし、そんなところにタイミングよく仕事を任せられて…。ディスクシステムはそんな時代だったと思いますね。
── 2年目の新人に1本のソフトを任せるなんて、いまではなかなか考えられないことですよね。
坂本 でも、本当はいまでもそういうことができたらいいんですけどね。でも当時は、デザイナーは絵が描けるので、当然ゲームもつくれるだろうという感覚だったんですよ。けっこうアバウトだったんですね(笑)。宮本(茂さん)もデザイナー出身ですし、デザイナーはみんな宮本のようなことができるだろうと思ってたわけですよ。
── あははは(笑)。
坂本 でも、それはすごい勘違い(笑)。だから、デザイナーを見たら、新人であろうが「何か1本やっとけ」みたいなことを言うようなところがあったんですが、それでも何とかなった時代でもあったんですね。「来月発売なんやけど」ってなれば、最後にはみんなでガッと力を出し合ってつくってましたし。いまやったら、間違いなく発売日を延ばしますよね。そのへんは勢いがあったというか、なんとかなった時代やったんですね。

任天堂からアドベンチャーゲームが出ない理由
── ディスクシステムの登場によって、ゲームジャンルの幅が広がったところもあったんでしょう?
坂本 やっぱり容量が増えたことで、面クリゲームから、ストーリー性がある広がりが出てきたりとか、つくる側としても選択肢は広がっていったと思います。『ゼルダ』のようなRPGも出てきましたし、ディスクシステムによってゲームの可能性を広げたことは大きいですね。
── 容量が増えたことで、『ファミ探』のようなアドベンチャーゲームがつくりやすくなったとも言えるわけですね。
大澤 アドベンチャーのようなストーリーが中心のゲームは、一度やったら二度とやらないんじゃないかという懸念もあって、任天堂としても手を出さなかったジャンルなんですけど、ディスクシステムは書き換えができるということで、やってみようということになったんです。それで、この時期に、『新・鬼ヶ島』や『遊遊記』(1989年)などを出すようになったんですよね。

── でも、ディスクシステムの後、任天堂発売のアドベンチャーゲームはほとんど出てませんよね。
坂本 そうですね。最後に出たのはディスクシステムの『タイムツイスト』(1991年)やったね。任天堂がどうかは別にして、僕としてはテキストアドベンチャーの仕組みをなかなか進化させづらかったという気持ちがあるんです。もともとコマンドがあって、その仕組みを変えていったのが、チュンソフトさんのサウンドノベルであったり、『逆転裁判』のシステムだったりしたわけですね。でも、『ファミ探』のように物語に乗っかっていくパターンとは若干違ってるところもあって…。その意味で、『ファミ探』のようなアドベンチャーが時代の流れに乗っかって、劇的に進化させられる部分をなかなか見つけられなかったことがありますし、アドベンチャー以外にもいろんなゲームをつくっていかなきゃいけない事情も当然ありましたし。そういう意味で、脇に追いやられたイメージが自分のなかにもあるんですね。あと、このような事件モノ、シリアスなものはキツイんですよね。表現もどんどん過激になったりとか、その意味でも手を出しにくいところがあったんです。さらに言うと、実際におこった事件のほうがエグかったり恐かったりもしますよね。その意味でも手を出しにくかったんですけど、今回ファミコンミニというカタチで出てきて、「このカタチはアリかな」と思ったんですけど、任天堂から新作を出すというのは今は難しいだろうなと自分は思ってるんです。

── 読者のなかには、もう何年にもわたって読者ハガキに「『ファミ探』の新作を遊びたい」ということを書いてくる人もいるんですが、やっぱり新作を出すのは難しいんでしょうか。
坂本 そのへんのことについては会社の意向もあると思うんですけど、僕自身としても、このように血の匂いのするものはやりづらいかなと思ってるんですね。
── 『ファミ探』や『新・鬼ヶ島』もそうだと思いますが、とても日本的なソフトがディスクシステムで登場しましたよね。それは、ディスクシステムがアメリカで出なかったということが理由だったりしたんでしょうか。
坂本 それはそうですね。でも、当時はとにかくディスクシステムで「どんなことができんのやろう?」とか、とにかく「産めよ増やせよ」という感じだったんです。そういう意味では難しいことを考えずに…。
── デザイナーが新人であっても「1本つくれ!」みたいな時代だったわけですね。
坂本 でも確かに、いまはインターナショナルなゲームを考える傾向がありますよね。当然販売本数が違ってきますし。でも、当時はとりあえず身の回りのことを考えてましたし、日本で売れるものは海外でも売れるだろうという考えもあったんです。だから、それほど海外のマーケットを意識してソフトをつくっていなかったですね。発想も自由でしたし、『ファミ探2』をやるときも、『1』でやり残したことがあるので「やらせてくれ」って上司に頼んでやらせてもらったところもありますので、そういう自由度はありましたよね。