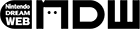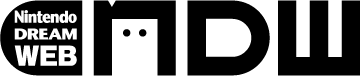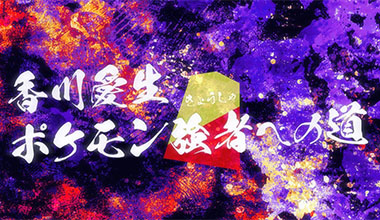マリオ映画公開記念!宮本茂さんインタビュー 制作の始まりから驚きの設定まで

「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」日本公開を前に、本作のプロデューサー・宮本茂さんのインタビューが実施されました。
制作の始まりから深い制作秘話、マリオたちのアッと驚く秘密まで、どうぞお楽しみください。
※映画の内容のネタバレはありません

Profile 宮本 茂
任天堂株式会社代表取締役フェロー。マリオの生みの親として知られる。
任天堂とイルミネーションの共同制作、その密な関わり
Q スーパーマリオの映画化における宮本さんの役割や、任天堂がどのように制作に関わっていたのかを教えてください
宮本:
本作は共同制作ですから、任天堂側も自分たちの制作物のひとつとして、スタートから「一緒に作りましょう」という形で始まりました。
配給のユニバーサル・ピクチャーズは、制作会社のイルミネーションおよびクリスさんに制作を委ねているので、僕とクリスさんがそれぞれのプロデューサーとして、すべてを決める役割になっています。それで、最初から二人で密に相談しながら、進めていきました。

── 任天堂の他の皆さんについては、どのような形で参加しているのでしょう?
宮本:
共同制作なので、両社のチームがプロジェクトに参加しています。
とはいえアニメーションを作るわけですから、監督からなにからイルミネーションのチームが圧倒的多数で、任天堂からは少人数になりますね。
任天堂からは、キャラクターを作ってきたチームのスタッフと、『ゼルダの伝説』シリーズとかでデモシーンなどを専門に作っているチームのなかから映画好きという人たちを集めて、「映画プロジェクトチーム」を作りました。
── 任天堂の皆さんは、どのような形で制作に臨んだのでしょうか。
宮本:
毎週、会議をして進めていったんですけど、映画好きを集めているので妙に舞い上がってしまって。すると映画好きなのでやっぱり、映画論みたいなものを語り出したりしちゃうじゃないですか。
それは禁止にしよう、と話しました。映画制作についてはイルミネーションが本業で、僕らは素人なわけですから。
だから任天堂チームの役割は、ゲームを作っている側として知っている情報をできるだけ提供することです。たとえば「ヒップドロップをしてほしい」とか、「クッパは振り回して投げてほしい」とか。
それ以外は、あくまで僕らは「ゲームをよく知っている観客」として意見を言うにとどめましょう、と。
もちろん、提案自体はどんどんしていって。それがちょっとずつ絵になっていくので、毎週のように絵をチェックして…。そういうキャッチボールで進めました。
── 他分野の、それも海外とのやりとりになるわけですね。
宮本:
そうですね。もちろん最初のころは直接ロサンゼルスに行っていたんですけど、結局ほとんどリモート会議だったんです。
というのも、イルミネーションはロサンゼルスにあってCGアニメの制作スタジオはフランスにあるので、もともとリモートでのやりとりなんです。だから、日本がそこに加わることにもあんまり抵抗がなかったようですね。
そういう点では、COVID‑19の影響で日本もリモートを取り入れるようになったことは不幸中の幸いで、リモート会議で絵を見ながら話す、ということを頻繁にやっていました。
企画から数えて約6年間、とても新鮮で楽しい制作でしたね。
Q 任天堂が映画の制作をするに至った経緯を教えてください
宮本:
マリオについては、デジタルゲームしかやらないってずっと言ってたんですよ。それには、きっかけがあって。
マリオが最初にブレイクした頃に、アメリカで「ミッキーマウスとマリオの人気調査」っていうのがあったんです。そのときミッキーマウスを抜いたんですよね、マリオが。
それでもてはやされて、「ミッキーマウスを抜きましたけどどんなお気持ちですか?」とか聞かれたりして。いやいや、40年、50年間生き続けているミッキーマウスと、新参者のマリオを比べるのがおかしいから、っていう話をしたことがあったんです。
そのとき、「ミッキーマウスはアニメーションと一緒に育ってきたのだから、マリオはデジタル技術と一緒に育てていこうかな」と、ふと思ったんですよね。
それで、新しいハードとともに、新しいマリオを1つ作ることにしたんです。
メモリーが4倍になって1つ、CPUが速くなって1つ。
そういう点では、いいきっかけになったできごとでした。
だから同じハード向けには、マリオのアクションゲームをあんまりたくさんは作っていないんですよ。過去の歴史をふりかえってもらえばそれがわかると思います。
[参考:主な「スーパーマリオ」シリーズ]
スーパーマリオブラザーズ(1985年/ファミリーコンピュータ)
スーパーマリオブラザーズ2(1986年/ファミコンディスクシステム)
スーパーマリオブラザーズ3(1988年/ファミリーコンピュータ)
スーパーマリオランド(1989年/ゲームボーイ)
スーパーマリオワールド(1990年/スーパーファミコン)
スーパーマリオUSA(1992年/ファミリーコンピュータ)
スーパーマリオランド2 6つの金貨(1992年/ゲームボーイ)
スーパーマリオ64(1996年/NINTENDO 64)
スーパーマリオサンシャイン(2002年/ニンテンドーゲームキューブ)
New スーパーマリオブラザーズ(2006年/ニンテンドーDS)
スーパーマリオギャラクシー(2007年/Wii)
New スーパーマリオブラザーズ Wii(2009年/Wii)
スーパーマリオギャラクシー 2(2010年/Wii)
スーパーマリオ 3Dランド(2011年/ニンテンドー3DS)
New スーパーマリオブラザーズ 2(2012年/ニンテンドー3DS)
New スーパーマリオブラザーズ U(2012年/Wii U)
スーパーマリオ 3Dワールド(2013年/Wii U)
スーパーマリオメーカー(2015年/Wii U)
スーパーマリオオデッセイ(2017年/Nintendo Switch)
スーパーマリオメーカー2(2019年/Nintendo Switch)
宮本:
そうやって育てているキャラクターを、映画とか小説とかにしようと思うと、好きな食べ物は何かとか、家族は誰がいるのかとか、ゲームに関係のない設定をたくさん決めなくてはいけないですよね。
次にどんなゲームを作るのかわからないのに、ゲーム以外のところで決めたルールでゲームが制限を受けるのは嫌だ、と。
ライセンスものがたまにあるのはいいとして、自分たちが作るマリオに影響するようなものは決めないようにしていたんです。
いっぽうで、映像コンテンツについてその頃の社長だった岩田(聡)さんといろいろ話をしまして。
任天堂がさまざまなコンテンツを発信していくなかで、せっかくだからゲーム機を持っていない大勢の人にも届くものをと、任天堂キャラクターIPを育てるという動きが出てきたんです。
それで、モバイルアプリはやろう、映画はやろう、ということがスタートし始めたんですね。それがもう、十数年以上前のことになります。
そこからまた数年が経つのですが、映画を作るのであれば、僕らが作りたい方向で自由にやりたいと思いました。
どこかからお金を出してもらうと自由にはできませんから、じゃあもう「自分たちで制作をする」って決めたほうがいいだろうという結論に至って。で、それからクリスさんに出会うわけです。
Q クリスさんと初めて会ったときに「物作りの仕方が似ていて盛り上がった」とおっしゃっていましたね。具体的にはどういった点でしょうか?
宮本:
いろいろあります。大事な物事の優先順位ですとか、問題が起こったときに答えを出す解決方法をどんなふうにするかとか。なかなか一言には表しづらい、細かい部分なんですけどね。
ひとつ話をするとすれば…。
ゲームって昔は完成してから発売まで1か月くらいあいだがあったんで、僕はその1か月の間に、チームの人とご飯を食べたりしながらダメだったところを話し始めるんですよ。
こういう話をすると、お前はネガティブなのか、って言われるんですけど(笑)。
みんなけっこう傷の舐め合いが好きなんです。「こうしておくべきだった」とか、「今からでも工場に行って直せるんなら直したい」とかお互いに言い出して。僕はさらにその傷口を開いて、塩を擦り込んで楽しむっていう。それを必ずするようにしていたんです。
── 反省点を指摘すると。

宮本:
というのも、発売して人気が上がるとすべて良かったような気になるし、人気が出ないと大失敗したような気になるじゃないですか。
結果を見てからそういうことを言うのは卑怯なので、結果が出る前に自分たちの考えを固めようと思っているんです。
これが実はすごく大事で、続編のネタや方針ってほとんどそこで決まるんですよ。だから、発売してから右往左往するようなことはあまりしないんです。
で、クリスさんって、そういう感じがするんですよ。
クリスさんは、僕と話をしているときに失敗したときの話をしてくれるんです。これをできる人ってすごいなあって。
(今の取材の場のように)メディアの皆さんにお世話になったおかげで、僕の過去の取材録というのがあって。
クリスさんは、僕がいろんな取材でしゃべってきたことを抽出して資料にまとめて、「ここ! 本当にそう思う」みたいなことを言い出したんです。
それはプレゼン術とかじゃなくて、クリスさんが素直にそういうプレゼンをしてくれたんです。こういうやり方は初めてでしたね。

宮本:
だいたいは、「私に任せればメディアスタジオとあの監督と、あの脚本家を連れてきて、あなたの作品をハリウッドで大成功する映画にしてみせる」みたいなプレゼンが多いわけです。
でも、あの人もこの人も知ってるって言われても、じゃああなたは何者なんですか、って思うじゃないですか。
実際に物づくりをしている人間はそういう勘がよく働くので、僕は、わりとそうでない人たちと一緒に仕事をすることが多くて。
「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のときもそうです。
運営のユニバーサル・パークス&リゾーツは、コンストラクションをやってきた人たちとか、設計してきた人たちが多いので、マネージャーのなかにもやっぱり作ってきた人が多いんです。
現場的な仕事をしているから、手がカサカサしているというか、肌艶があんまり良くなかったり。この人作っているなあ、って感じがして。
そういう人に出会えたので、やろうとなりました。
だから、クリスさんと出会えたのもすごく幸せだなと思ってます。
彼はすごい高みにいる人ですからね。そういう人と普通に話をして仕事ができているっていうのは、すごいことだと感じています。
── 同じような空気感で、制作ができたと。
宮本:
ただ制作の終盤、僕は「監督が次はもうコリゴリだって言っていないか」ってことをすごく気にして、クリスさんに何回もメールしてたんです(笑)。
というのも、ここの演出はこうじゃないと思うとか、たまに監督の領域まで口を挟んでしまうんですよ。ディレクターの域に入ったらあかん、プロデューサーなのに、と思いながら。
── たとえばどういった…?
宮本:
笑ってしまうような内容なんですけど。
たとえば、ルイージがマリオを追いかけて、建物から出るシーンがあるとするじゃないですか。ドアを開けっぱなしで行くんで、(遠慮がちに)ルイージは閉めてほしい…って(笑)。
今さらできない、その秒数の尺がもう入れられない、とかいろいろ言われたけど、気が付いたら入っていたり。
水中の生き物からポコポコって泡(あぶく)が出るシーンで、このポコポコのあとに最後もう1個ポコって出してほしい、とか。
そんなやりとりしながらどんどん入り込んで、最後は「OK!」っていうところまで細かく作って。
そういうのがあったので、監督が「二度と御免」とか言ってない? って心配してたんですけど。むしろ監督は完成する前から、「この仕事は続けたい」とずっと言っていると。その言葉にすごく救われたりしました。
本当にみんな仲の良い制作現場で。
珍しいですね、これだけ年月をかけて作っているのにみんな仲良くいられたっていうのは。
── 我々の想像以上に、どっぷり関わっているんですね。
宮本:
だから、今回の映画に関しても「作ってくれたものを見て僕がどのように感じたか?」みたいなことを聞かれると、それはニュアンスがちょっと違って。一緒に作り上げていったものなんですよね。
Q マリオというキャラクターが映画になることについて、個人的な思い入れなどを聞かせてください。
宮本:
舞台挨拶でもお伝えした通り、「ああ、やっと人間になったな」って。
▼舞台挨拶の様子はこちら


宮本:
僕は昔、漫画を描いていたんです。任天堂にはデザイナーとして入社しましたが、仕事はもちろん漫画とは全然関係なくて。
工業デザインを学んでいたので、アーケード筐体の本体やコインの投入口とか、コントロールパネルを作ったり、カタログを作ったりしていました。
そのうち、ゲームの中の絵を描くようになって。それでもまだ漫画とは関係がなかったんですが、『ドンキーコング』を作るときに、「あれ、これはひょっとしてアニメーションにできるかな?」と思って。
ただのドットを描くのではなく、アニメーションをやろうと思ったんです。
それで、『ドンキーコング』のマリオを3コマで動かしたら、けっこう動いている感じがしたんですよね。
そうすると、自分がアニメーションのようなこと…漫画がアニメーションになるというところを、仕事にしていけるのかもと。ゲームデザインという仕事自体も、デザイナーがゲームを作るっていうことも、まだなかった時代ですから、それが仕事になるなと思ったんですよね。
時代が進んで、『スーパーマリオ64』で3Dモデルにしたら、もっともっとディティールを出していけるようになって。
僕は小学生のころ、人形劇の作家になりたかったんですよ。
NHKで「ひょっこりひょうたん島」という人形劇があって…若い方はもう、ご存知ないかな(笑)。その前に「チロリン村とくるみの木」という人形劇があったりもしたんですけど。

それで、パペットショーをやりたいとずっと思っていて。NINTENDO 64で3Dになったときに、けっこうそこへ近づいたな、この先はパペットショーをどう進化させるかだな、と思っていたんです。
ところが、実際に映画を作るとなると、ちょっと心配になってきたんです。「マリオが巨大なスクリーンで動いて、本当にこんなディティールでいいのだろうか」とか。「お客さんはどう思うんだろうか」とか。
けれど今回、クリスさんやアニメーターさんたちといろんな話をしながら作っていったんですが、出来上がってみたら「大丈夫、人間になってる」って、ちゃんと自分で感じることができました。
それでパリのスタジオに向けて、「おかげさまで、マリオが人間になりました!」っていうビデオメッセージを送ったりしたんです。
大きなスクリーン向けに作るということとか、それぞれの登場人物の動機みたいなものを少し作り込んでいこうとしたことで、マリオが人間になったなと。うれしさもひとしおです。
── 過去にも宮本さんはアニメ映像作品として「ピクミンショートムービー」を作られていましたが、そこから今回の映画に活かした部分はありますか?
宮本:
それはとくにないですね。「ピクミンショートムービー」は、自分としては4コマ漫画の延長だったんです。

宮本:
4コマ漫画の起承転結みたいなものを使って、もうちょっと『ピクミン』らしい不思議なものを作りたいと。
最初のプランでは、生き死にに対してとくに興味を示していないピクミンたちを見て、人が何を感じるか…というちょっと哲学的なことも含めた、不思議な4コマ漫画を作れないかなと思っていたんです。
ただちょうどあのころ、これから任天堂のIPを映像化しようという動きがあったので、岩田さんに相談して。それで、目的は商品化ではないんですけど、とりあえず『ピクミン』でショート映像を作ってみたらいいんじゃないか、と。
だから、今回の映画にはあまり関係なかったですね。動画を作って全部を見るって難しい…ということを体験したことくらいでしょうか(笑)。
今回の映画でも、ちょっと哲学っぽいことを言う不思議なキャラクターが出てきたりはするんですけど。
商品を作るっていうのは、全然また違う仕事なんですよね。